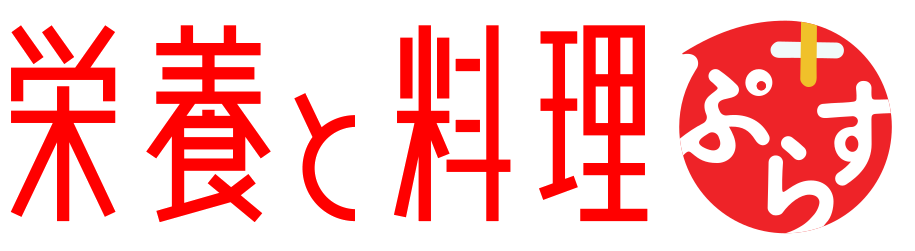エルサルバドル
文と写真/岡本啓史(国際教育家)
¡Buenos días!
エルサルバドルでは、公用語のスペイン語で「¡Buenos días!(おはようございます)」が一般的な朝のあいさつですが、じつは先住民ナワト族の言葉では「¡Yek peyna!」(イェクぺイナ)ともいいます。ナワト語はエルサルバドルにおいて事実上、唯一の先住民言語といわれています。先住民大虐殺という苦い歴史による人口減少に伴って話者は多くありませんが、ナワト語の復興活動があるなど、国の文化の一部として今もたいせつにされています。
マヤ文明の影響を受けたエルサルバドルの食文化
さて、エルサルバドルと聞いて、皆さんはなにを思い浮かべますか?
「え、どこ?」「どんな国?」「名前がいいにくい」など、あまりピンとこないというかたもいるかもしれません。実際にエルサルバドルは、日本ではあまり知られていない国の1つともいわれています。
エルサルバドルは「アメリカの小さな親指(El Pulgarcito de América)」と呼ばれるほど国土が小さいですが、歴史、伝統、そして食文化が豊かな国です。中央アメリカに位置するこの国には、マヤ文明の影響を受けた伝統料理が今も受け継がれ、人々の暮らしの中でたいせつにされています。

エルサルバドルのサンタ・アナ大聖堂。ラテンアメリカの他の大聖堂(バロック様式)と異なり、ゴシック様式で建てられている。
今回は、エルサルバドル出身のジョアナ・サンタマリア(Johanna Santamaría)さんの朝食を紹介します。
ジョアナさんは、国際開発のコンサルタントとして、プロジェクトの評価・モニタリングや研究などの仕事をしています。プライベートでは、時間さえあればどこかに移動する生粋の旅好きです。「異文化や新しい学びに敏感であり、旅を通してユニークな場所や人に会い、一度の限られた人生でつねに楽しんで生きていきたい」という、ラティーナ(ラテン系の女性)らしいパッションあふれるかたです。
エルサルバドルの国民食「ププサ」
そんなジョアナさんの今回の朝食には、日本人が聞くと、その響きがかわいらしく感じられる「ププサ」という料理が登場します。

ジョアナさんとププサ(右)、トマトベースのソース(中央)とサラダ(左)
ププサは、その伝統、汎用性、低コストにより、エルサルバドルで最も人気のある食べ物の 1 つです。作り方は、生地の中に具を詰めて丸く成形し、ハンバーグを作るときのように両手でペタペタと投げ合って平たくしてからフライパンで両面を焼きます。起源は不明ですが、同国の美食を代表する国民食といえるでしょう。厚めの生地(とうもろこし粉または米粉のトルティーヤ)には、チーズ、リフライドビーンズ(フリホレス)、豚肉をカリカリになるまで揚げたチチャロンなどの具材が詰められています。


〈左〉米粉で作った生地。〈右〉 生地に具を詰める様子
人と人とをつなげる「ププサ」の魅力
ププサはエルサルバドルの美食の象徴であるだけでなく、文化的なつながりの手段でもあるようです。ジョアナさんにとってププサとは?と尋ねたところ、「単なる食べ物ではなく、ププサなしにエルサルバドルは語れない、自分のアイデンティティの1つである」と答えてくれました。彼女は、外国出身の同僚や友人と自国のルーツを共有する手段とし、人とつながるきっかけとしてププサを共有することがあるそうです。そして「だれかといっしょにププサを食べるのは、エルサルバドルへの窓を開くことだ」と語ります。
また、ププサは屋台でも家庭でも簡単に作れる料理なので、週末は家族でいっしょに食べたり、友人と街に出て屋台でププサを楽しんだりすることができるなど、同国の生活に深く根づいている料理だそうです。


〈左〉職場の同僚と共にププサを準備する様子。〈右〉いわゆる「作りおき」、あるいは友人や家族と食べるために多めに作るというププサの生地。
外からは中身があまり見えないため、一見、穀物の粉の生地を焼いただけに見えるのですが、ププサは具材もあるので、たんぱく質や炭水化物、脂質をバランスよく摂取できる栄養価の高い料理です。そして、重要な「味」に関しては申し分ありません。さらに、この料理は体に栄養を供給するだけでなく、前述のとおり、エルサルバドルについてもっと知りたい人たちへの”文化の架け橋”としても機能します。エルサルバドル人のこだわりが、この直径10cmほどのププサに凝縮されているといっても過言ではないでしょう。ププサは、今後も多くの人たちにとって「エルサルバドルの味と物語」を発見するきっかけとなり、人と人とのつながりを紡いでいくことと思います。
「中米の日本」とも呼ばれるエルサルバドル。その理由は?
日本からは遠い位置にあるエルサルバドルと日本はあまり縁がないように思うかもしれませんが、意外といろいろなつながりがあります。以下にその例と理由をあげてみます。
- エルサルバドルでは、豆を多用する食文化が根づいているーーこれは、日本のみそや納豆などの発酵食品と共通する点があり、豆の持つ栄養価や風味をたいせつにしているという点で似ています。
- エルサルバドルは地震や火山活動が活発な国であり、日本と同様に自然災害のリスクが高い地域であるーー日本はJICA(国際協力機構)を通じて防災対策や耐震技術の導入を支援してきました。
- 日本の算数教育がエルサルバドルの学校教育に取り入れられた事例があるーー教育を通して両国のつながりもあります。
これらのほか、エルサルバドルは細くて狭い地形と資源の乏しさ、勤勉な国民性という日本との共通点があることから「中米の日本」という呼び名がついているともいわれています。
モザンビークで出合った、エルサルバドルの食文化
筆者がエルサルバドルの食文化を知ったのは、アフリカのモザンビークででした。現地で暮らしていたときに「世界の料理を学びたい」と思い、共通の友人を通してつながったのが、当時筆者が住んでいたアパートの目の前に住んでいたジョアナさんです。
二つ返事で快く家に招待してくださり、そのときに教えてもらったのが、まさに今回のププサでした。説明しながらププサを素早く器用に包むジョアナさんを目前に、何回も作ってきたに違いないと実感させる「職人業」の印象を受けました(そして筆者は初めてのププサ作りで、彼女の何倍も時間がかかりました。)
このように食をきっかけに始まったつながりですが、当時ジョアナさんはWFP(国連世界食糧計画)に勤務しており、国際支援業務に携わっていた筆者と同業者という共通点から、さらに親近感がわきました。その後、彼女とはヒスパニック系のハウスパーティ(スペイン語を話す人たちがそれぞれ自国の料理を紹介して味わう会)でも何度かご一緒し、おいしく楽しいひとときを過ごしました。
ジョアナさんはモザンビークからエルサルバドルに帰国後、USAID(アメリカ国際開発庁)の支援プロジェクトにかかわる仕事をしていましたが、最近の政権交代の影響でプロジェクトが中断されるというきびしい状況に直面しました(※政治的な詳細には触れませんが、国際支援の現場ではこうした影響を受けることも少なくありません)。そんな彼女と再びつながるきっかけとなったのが、今回の朝ごはん企画です。食を通じて文化を学び、遠く離れた友人との絆を再確認できるのは、とても貴重なことだと改めて感じました。

左から右回りに筆者 、スペイン人、ホンジュラス人、エルサルバドル人のジョアナさんと、チリ人。写真の料理は、スペイン料理のスペイン風オムレツとサルモレホ(スープ)
エルサルバドルの朝ごはんには、家族やコミュニティをつなぐ力があります。ププサを囲むひとときは、ただおなかを満たすための食事ではなく、人々の絆を深めるたいせつな時間でもあります。
日本ではあまりなじみのないエルサルバドルですが、この記事を通じて、その魅力や人の温かさを感じていただけたら幸いです。
次回はどの国の朝ごはんが登場するのか、どうぞお楽しみに!

| 【筆者プロフィール】岡本啓史(おかもと・ひろし)●国際教育家、生涯学習者、パフォーマー。これまで国連やJICA等で5大陸・45カ国の教育支援を実施。ダンサー、役者、料理人、教師の経歴も持つ。学びに関するブログを5言語で執筆し、ライフスキル教育、講演活動、グローバル学び舎3L-ミエル運営など、日本内外で国際理解・幅広い学びやウェルビーイングの促進に注力中。著書『なりたい自分との出会い方:世界に飛び出したボクが伝えたいこと』(岩波書店)『せかいのあいさつ』全3巻(童心社)監修。サイト/SNS:https://linktr.ee/mdhiro |