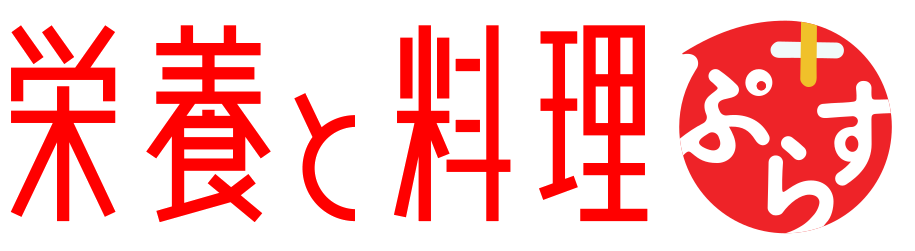ギニア共和国
文と写真/岡本啓史(国際教育家)
Galer!
ギニアでは、地域や民族によってあいさつの言葉が異なります。今回ご紹介するかたの現地語は、ギニア森林地域に住むゲルゼ族の言葉で、朝のあいさつは「ガレ!」といいます。
ご存じですか? 4つのギニア
いきなりですが、皆さん、「ギニア共和国」をご存じでしょうか?
「え、どこ?」「なんとかギニアという国の名前は聞いたことある」「どんな国?」と思うかたもいるかもしれませんが、実際にギニア共和国は、日本ではあまり知られていない国の一つともいわれています。
「ギニア共和国」は西アフリカに位置し、首都はコナクリ。そのため「ギニア・コナクリ」と呼ばれることもあります。フランス語を公用語としていますが、国内には多数の民族と文化が存在し、それぞれの地域で異なる言語が使われています。
ギニア共和国は豊かな自然と多様な文化を持つ国ですが、その名前には特別な背景があります。じつは、「ギニア」という名前がつく国は世界に4つあり、ギニア共和国以外にも「 赤道ギニア」、「ギニアビサウ」、そして「 パプアニューギニア」 があります。そのため、ギニアの人々は自分の国を「ギニア共和国」や「ギニア・コナクリ」とフルネームで伝えることが多いそうです。(日本でも、同じ姓の人同士を区別するためにフルネームで呼ぶことがあることに似ているかもしれません)。
ちなみに、この4つの「ギニア」の公用語は次の通りで、名前は似ていても、言語や文化、歴史的背景はまったく異なることがわかります。
• ギニア共和国:フランス語
• 赤道ギニア:スペイン語
• ギニアビサウ:ポルトガル語
• パプアニューギニア:英語
「ギニア」という言葉は「黒人たちの土地」を意味するベルベル語が由来という説が一般的ですが、ヨーロッパの植民地政策の影響が見え隠れしています。今回は、ギニア共和国に住むマリエ・クレーさんの家庭の朝ごはんを紹介します。

ギニアの首都コナクリにあるグラン・モスク。
ギニアの朝ごはん「ラフィディ」
マリエ・クレーさんは、ポルトガル人のパートナーとの間に2人の子どもがいます。西アフリカでは大学に進学する人が少ないといわれていますが、彼女はギニアの大学で国際関係史を学び、カーボ・ヴェルデ(アフリカの北西沖に浮かぶ火山群島の国家)で人事学の修士号(修士論文は同国公用語のポルトガル語)を取得するなど、学習意欲に満ちあふれています。子育てや家族との時間を大事にしながらも、ランニングや料理、その他の習い事など、趣味をたくさん持ちながら自分の時間をたいせつにしています。

マリエ・クレーさん(右)、パートナーのエマヌエルさん(左)、中央はマリエ・クレーさんの母親。
今回ご紹介するマリエ・クレーさんの朝ごはんは、ギニア共和国の国民的料理ともいえる米料理の「ラフィディ」です。

色とりどりのラフィディの材料。
ラフィディは、野菜と米を使った素朴な料理で、地域の特産品が生かされています。作り方は以下のような流れです。
1 野菜を煮込む
野菜(オクラ、なす、とうがらしなど)を塩とともに煮込みます。
2 野菜をつぶす
煮込んだ野菜をいったんとり出し、伝統的な木製のすり鉢でつぶしてペースト状にします(写真右上にある緑色のもの)。
3 米を炊く
野菜を煮込んだ汁で米を炊き、香り高いごはんに仕上げ、パーム油をかけます。
4 仕上げ
特製スパイス「スンバラ」(写真左上の黒いもの)を用意します。
5 楽しみ方
すべての材料を混ぜて「混ぜごはん」として楽しみます。


〈左〉パーム油。〈右〉ギニアの混ぜごはん「ラフィディ」。
ラフィディは、ギニア共和国ではおもに家族が集まる場や、地元のお祝いごとで食べられることが多いそうです。その素朴でやさしい味わいから、忙しい日常の中で少しホッとするひとときを提供してくれる一品でもあります。
ギニア共和国と日本の共通点とは?
一見、遠く離れている日本とギニア共和国ですが、じつは食文化に共通点があります。それは、「発酵食品をごはんにかけて食べる」こと。
既述の「スンバラ」は、ギニア共和国を含む西アフリカでよく使われる調味料です。ネレ(Néré)と呼ばれるマメ科の木からとれる豆を煮て、乾燥させてから発酵させたもので、多様な民族や現地語が使われている西アフリカ諸国それぞれで、異なる名前で呼ばれています。好みに応じて干しエビやその他のスパイスを混ぜ、乳棒で粉砕することでミックススパイスとなり、風味豊かに仕上がります。この香りと味は、ギニア共和国料理のかなめだといわれているようです。
調味料とはいえ日本のみそと違って塩を含まず、発酵方法としては納豆の系譜に属する食品であり、においも独特で糸を引くことから「西アフリカの納豆」とも呼ばれています。スンバラと納豆といった発酵食品が、両国で日常的に愛されているだけでなく、どちらの国も「ごはんにかける」点は興味深いですよね。さらに、最近では「大豆からスンバラを作る」人もいて、まさに納豆と近い存在になりつつあるのかもしれません。

西アフリカの納豆ともいわれる「スンバラ」
そのほか、ギニア共和国と日本の意外なつながりといえば、タレントのオスマン・サンコンさん。ギニア出身で、元外交官のサンコンさんは、日本とギニアの友好関係の構築に注力しています。
筆者とマリエ・クレーさんとのつながり
最後に、私がマリエ・クレーさんと出会うきっかけとなったのは、アフリカのモザンビークでの経験です。元ポルトガル領土のモザンビークでは、言語の観点からも、ポルトガル人が住み込みで仕事をしているケースがよくあります。もともと食べやすくておいしいポルトガル料理を学んでみたいと思っていた私は、モザンビークのポルトガル人コミュニティに「料理を教えてほしい」と声をかけました。そこで快く引き受けてくれたのが、マリエ・クレーさんのパートナーのエマヌエルさんでした。
「教えてあげるから家においで!」とやさしい声をかけてくださったので、訪問したところ、ドアをあけて快く迎えてくれたのが、マリエ・クレーさんでした。
日本人の私とチリ出身の妻と同様、異文化や世界の食に興味がある国際結婚カップル同士という共通点もあり、すぐに仲良くなりました。そこから、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、南米の出身者が料理を介して文化交流をするという、豊かなコミュニケーションが生まれていったのです。世界には多様な食文化があり、食を通じていろいろなつながりが見えてくるものです。「食」は世界をつなぐ貴重な要素であることを、マリエ・クレーさんらと交流する中で、再認識しました。


〈左〉台所で談笑するマリエさんと手にバカリャウ・ア・ブラス(ポルトガル定番の干し鱈の料理を持つエマヌエルさん。〈右〉カルド・ヴェルデ(ケールのスープ)を作るマリエさん。

〈上左〉ポルトガル料理とワインを楽しんだあと、日本酒と日本のスナックで乾杯する異文化交流中。
★マリエさん家族がポルトガルで立ち上げている宿泊・観光施設のリンクはこちら:https://doliviahomes.pt

| 【筆者プロフィール】岡本啓史(おかもと・ひろし)●国際教育家、生涯学習者、パフォーマー。これまで国連やJICA等で5大陸・45カ国の教育支援を実施。ダンサー、役者、料理人、教師の経歴も持つ。学びに関するブログを5言語で執筆し、ライフスキル教育、講演活動、グローバル学び舎運営など、日本内外で国際理解・幅広い学びやウェルビーイングの促進に注力中。著書『なりたい自分との出会い方:世界に飛び出したボクが伝えたいこと』(岩波書店)『せかいのあいさつ』全3巻(童心社)監修。サイト/SNS:https://linktr.ee/mdhiro |